 深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ インフレに強い投資!安心ポートフォリオの作り方
インフレは現金の価値を目減りさせますが、株式や不動産投資信託(リート)を活用することで、影響を軽減できます。たとえば、国内株式と先進国株式、新興国株式のインデックスファンドを組み合わせることで、幅広い分散投資が可能です。また、不動産価格や賃...
 深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ  深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ  深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ  深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ 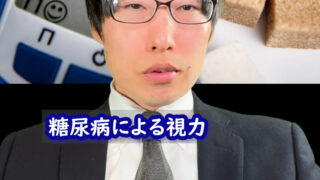 深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ 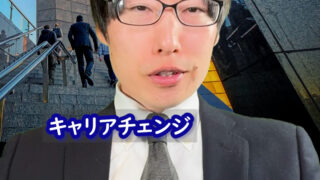 深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ  深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ  深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ  深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ  深掘り解説とまとめ
深掘り解説とまとめ